| 写真散歩 東高野街道 石清水八幡の門前町を歩く 2012 梅雨空 (その3) |
||||||
 |
||||||
| 行宮跡からまた少し行くと、らくがき寺こと「単伝庵」に着きます。お堂の壁にらくがきのできるお寺として有名なので、一度あしを運んでみたいと思ってました。 |
||||||
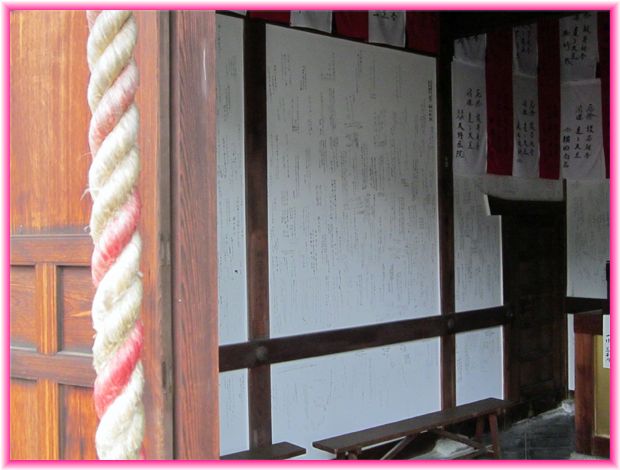 |
||||||
| 境内の大黒堂の壁にらくがきをしても良いようです。その外の壁などには一切ダメですよ(笑) 行くまでは、「ショウモナイ言葉の羅列ばかり並んでるだろう。」と、思ってましたが意外と真面目な言葉ばかりで、ちょっと期待ハヅレ(^^ゞでした。 簡単に言うと、大きな絵馬のような感じで、みなさんお願い事や嬉しい事や心配事などを、率直に神様に申告されてます。わたしもひとつお願いを書き込んでおきました。 (写真は、個人情報も写りこんでるのですこしぼかしてます) |
||||||
 |
||||||
| らくがき寺をでて、八幡宮にもどる途中に、飛行神社があります。この神社は、飛行原理を発見した二宮忠八が、飛行機事故殉難者の御霊をお祭りするために自宅地内に創設した神社です。 ギリシャ神殿を思わせるモダンな拝殿と純粋な神社建築のアンバランスが目を引きます。境内には二宮忠八の資料館や航空機に関する展示がたくさんありますが、残念ながらあまり興味がわかなくてパスしました。 |
||||||
 |
||||||
| 八幡宮からの下り道にきました。 ここには謡曲「小鍛冶」の舞台とされる相槌稲荷があります。謡曲のあらすじによれば、「刀匠三条小鍛治が稲荷明神の化身の少年を相槌を受けて石清水の名水を使って、名刀小狐丸を鍛えたところ。」とされています。 正月などにこの付近を通っても、ものすごい人出と露天の呼び込み(^^)で、こんなちいさなお宮など気にすることがありません。 今回ガイドブックでみつけてはじめて手を合わさせてもらった次第です。 |
||||||
 |
||||||
| 稲荷から旧街道にでるところに「松花堂旧跡」という石碑のある泰勝寺があります。これから向かう松花堂庭園のところに移る前に松花堂昭乗が住持していたお寺の跡だそうです。 お参りしてお話を聞こうとおもったのですが、あいにくと「今日は法事で一般の参拝は遠慮してもらっています。」とのこと。 残念です。 |
||||||
 |
||||||
| 旧街道に出たところで「まちかど博物館 城ノ内」を見つけて寄らせてもらいました。ここは、いわゆる個人博物館で、自宅の一角に展示スペースを設けて資料などを見せていただけます。 私の訪れた時は「旧東高野街道八幡の今昔」というテーマで明治から昭和30年代と今の風景を並べた写真や、当時の生活用品などが飾ってありました。 館長さんのお話では、「ひと昔前の八幡駅前は商店街として栄え、樟葉や田辺の松井・大住地区からも買い物に来ていた。この家も昔は履物と自転車を扱うお店だった。」とのことです。 興味をひいた鉄道関係では、昔の京阪電車や京阪バスの写真、明治時代と思われる汽車、汽船、自動車、自転車、飛行船!などが走る回るデザインのポスターがありました。 その他、ガイドブックに出ていないようなちいさな見所なんかも教えていただきました。今後行かれる方はぜひ寄ってみてください。参考になりますよ。 |
||||||
 |
||||||
| 博物館を出て、大通りから路地に入り込んだわかりにくい場所に、ブログで紹介した女郎花塚の相方、頼風塚があります。 ブログとダブりますが 「謡曲「女郎花」の舞台とされ、傍らの説明板によれば、 昔、男山の麓に住む小野頼風と深い仲となった都の女が、男の足が遠のいたのを恨み悲しみ、男山を流れる放生川に身を投げた。女の脱ぎ捨てた衣が朽ちて女郎花がとなった。この花を折ろうとすると恨みがましく逃げていく。その姿を見た男は、嘆き悲しんで後を追って入水した。 里人は、女の塚を女郎花塚、男の塚を頼風塚と言うようになった。 との伝承があります。 |
||||||
| このコーナーで使用しております背景のスイレンのイラストは、素材集「ブルーデージー」よりお借りしたものです。無断転載はお断りします。 | ||||||
Home |
Back |
Next |
Index |
|||